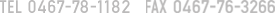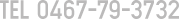すでにこのHPでも伝えているように、『ラリーモンゴリア2014』において、
TEAMアピオの尾上 茂/森光 力組がクラスAで見事優勝を果たした。
齢67にして、いまだ現役ラリーストとして活動を続ける、アピオ株式会社会長の尾上茂。
尾上がモータースポーツにかける情熱、そしてアピオのアイテムには、
他ブランドではありえないある”関係”があった。
まずは「走れる」と考えるのが尾上流
僕が四輪駆動車専門誌の編集部に入ってすぐに、あるレース取材を命じられた。かつてあった日本四輪駆動車協会が富士スピードウェイのオフロードコースで開催していたもので、協会の頭文字から通称「JFWDA戦」と呼ばれていた。
富士スピードウェイのオフロードコースというのは今は無くなってしまったが、あの伝説の30度バンクのすぐ脇に設置されていた。スーパークロスも真っ青の難コースで、そこを重量級のクロスカントリー4WDがバイクに負けじと飛んだり跳ねたりするわけである。レースの迫力もさることながら、レースのために造られたマシンがクラッシュする様も観客を魅了するファクターとなっていたのである。
そんな激しいレースの中で、いつも小さなジムニーで飛んでいたのが尾上茂である。JFWDA戦はクラス混合レースであったので、ジムニーは上位クラスのパジェロやビッグホーン、Jeepなどと一緒に走らなければならなかったのである。大きなマシンに混じって、小さなジムニーが走る様を初めて観た時“大丈夫か?”と感じた記憶がある。
だが尾上がドライブするジムニーは、格上のマシンと肩を並べてコースを疾走した。
「正直、最初はJFWDA戦なんてと思ってたんだよね。でも、初レースは1周目でリタイヤ。ディストリビューターのコードが衝撃で外れてたんだよ。」
最初の頃は、いつも何かしらのトラブルがあったと尾上は回想する。だが、そのトラブルをリカバリーする度に新しいパーツが生まれた。特にテーパーリーフスプリングなど新しい足周りパーツが多く生まれた。アピオの『ROADWINシリーズ』をはじめとするサスペンションは高い性能を有していると評判だが、その礎はJFWDA戦が始まりだったと尾上は回想する。そして、APIOというブランドの出発地点がここにあった。
「まずは走れると思って行くんだけど、走れない場合があるんだよ。だから、どうしたら走れるかを考える。そしてパーツを造ったり、クルマをいじったりね。」
3年ほどJFWDA戦を走っていると、いつの間にかクラスで常勝するようになった。すると、彼の情熱はさらなる高みに向かってしまったのである。「なんかもういいかなと思ってて。オーストラリアに行った時に向こうの友人から“オーストラリアサファリっていうレースがあるぞ”と言われたんだ。だからそれがいいやって、参戦することにしたんだよ。」
この時のことも、よく覚えている。当時の日本は好景気で、四駆業界も空前のブームに湧いていた。だから、ちょっとしたオフロードレースに出たり、参戦マシンをスポンサードするパーツメーカーはあったが、社長(当時)自らがラリーに出てしまうメーカーやショップはまずなかった。それゆえ尾上の参戦は、業界でもかなりの話題になったものだ。オーストラリアンサファリは海外ラリーレイド。日本の草レースのJFWDA戦とはワケが違うと。
1989年、尾上は市販車改造部門のエスクードでオーストラリアのアウトバックを疾走。結局、このラリーレイドには95年まで出場し、クラス優勝5回、95年には総合6位も果たした。このラリーから生まれたエスクード用パーツもまた、アピオの看板商品となっていく。