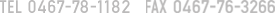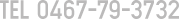かつては高級ホテルエリア、いまは新シーフロント。これが東京・品川の現代のイメージだと思う。駅を出ると、南口も北口も華やかでかつての品川を伺い知ることはできない。現代において「品川=海辺」と考える人はまずいない。ところが品川は、昭和初期までまさに海沿いの場所だった。
明治半ば、当時の東京市は東京湾に大型の船舶を入港させるため、隅田川下流域を中心に水深を深くする工事を計画した。この時に発生する泥土を埋め立てに使うということになり、これが品川から羽田の埋め立て地造成に発展したらしい。
品川沖は昭和2年から埋め立てが開始されたというので、今のような景色になったのはそんなに昔ではないということになる。たしかに1954年に公開された映画「ゴジラ」では、まだ品川はそれほど埋め立てられていないように見える。余談だが、映画の中でゴジラが東京に上陸した場所「八ツ山橋」が、今回の目的地の品川宿の入り口になる。
話を戻すが、かつての品川は風光明媚な海沿いの町だった。そして江戸時代までは、東海道五十三次を代表する大きな宿場町「品川宿」だったのである。日本橋から数えてひとつ目、さほど距離の離れていない品川宿だが江戸の人々には欠かせない場所だったようだ。
京都から“下って”きた人は江戸市中に入る前にわざわざここで一泊して身綺麗になってから市中に入ったというから、昔の人は実に粋だったわけだ。逆に江戸に住む人々にとっては、品川は泊まりで行く歓楽街だった。「土蔵相模」など、旅籠とも遊郭ともつかない店が並び、江戸っ子の粋を満足させていたのだ。ちなみに新橋愛宕山下や上野山下、谷中、内藤新宿(今の新宿2丁目、3丁目あたり)などには飯盛り女や茶屋女に春を売らせる店が並んだとかで、もっぱらお上も目をつぶった半公認の風俗エリアが江戸には多かったようだ。
当時の品川宿の風俗は、映画「幕末太陽傳」に詳しいので、時間のある方はぜひご覧いただければと思う。この映画の舞台も土蔵相模になっている。