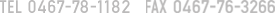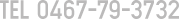観音崎は三浦半島側では東京湾の先端にあたる場所だ。それ故、首都防衛の要とされてきた。特に欧米列強の脅威が深刻化した明治中期になると、政府は清国やロシアの侵入を想定した東京湾要塞計画を推進したのである。
東京湾要塞は、第一、第二、第三の各海堡を中心に、三浦半島、房総半島の各地の砲台で形成する軍事施設の集合体だ。関東大震災によってその多くは甚大な被害を受けたが、今も多くの遺構が残っている。
観音崎にも8つの砲台が設けられ、いまもその跡を見ることができる。ジムニーを降りて、岬の山中を散策してみると突如レンガ造りの砲台跡が現れる。軍事施設だったわけだが、今見るとそのレトロな雰囲気と深い緑のコントラストが幻想的だ。
注意して見ていただきたいのは、同じレンガ造りでも積み方に違いがあるということ。明治期の日本のレンガ建築には主に、ふたつの種類があった。ひとつめはフランス積み(正式にはフランドル積み)。ひとつの列に長手と小口が並んで見える積み方だ。もうひとつはイギリス積み。こちらは一段は長手、その上は小口、さらに上はまた長手と交互に積んでいく方法。当初、日本はフランス積みを採用していたが、イギリス積みのほうが合理的で強度も強いため、明治20年以降の建築物はほとんどイギリス積みになっている。
現在、観音崎には8ヶ所の砲台跡が残っており、海上自衛隊施設内にある第四砲台を除いてすべて観ることができる。そのほとんどがイギリス積みだが、皆さんも訪れてその違いを確認してみると面白いと思う。